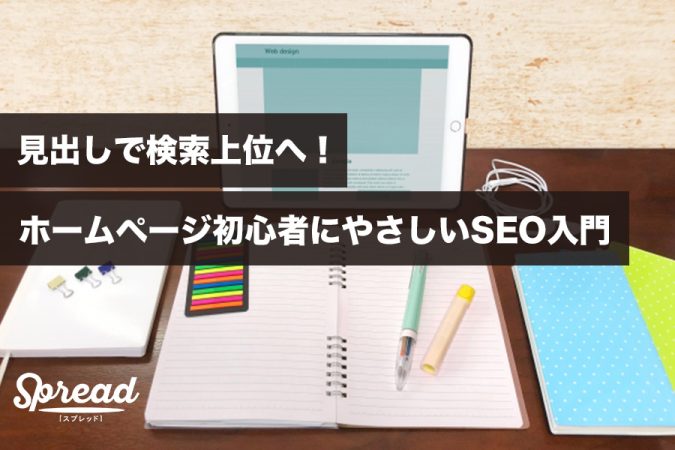
ホームページ作成を自分で始めたいけれど、見出しやSEOのことがよくわからない…。そんな初心者の方でも、この記事を読めば、すぐに使える知識とコツが手に入ります。
1. 見出しってなに?どうして大切なの?
1-1. 見出しの意味と役割
1-2. 読みやすくするための工夫
2. SEOってなに?見出しとどんな関係があるの?
2-1. SEOの基本をやさしく説明
2-2. 見出しが検索に関係する理由
3. 効果が出やすい見出しの作り方
3-1. キーワードの入れ方と注意点
3-2. 文字数はどれくらいがいい?
3-3. パッと見て内容がわかる言い方にする
4. 見出しのつけ方ルール:「h1」「h2」ってなに?
4-1. 見出しの順番と使い方のコツ
4-2. WordPressでもできるシンプルな操作方法
5. 見出しをチェックする便利な方法
5-1. 見出しスコアとは?
5-2. もっと良くするためのポイント
6. よくある質問

ホームページやブログを作るとき、「見出し」を使うと読みやすくなります。見出しは、長い文章の中で大事なところを伝えるための目じるしのようなものです。文章の内容をひと目で伝える役わりがあり、読んでいる人がどこに何が書いてあるかをすぐに理解できます。うまく見出しをつけると、ページ全体がすっきりして、読む人にやさしいページになります。
見出しは、言ってみれば「小さなタイトル」です。たとえばレシピの記事なら、「材料」「作り方」「ポイント」などの言葉が見出しになります。これがあるだけで、「このあと何が書いてあるのか」がわかりやすくなります。また、文章の流れを整理する役目もあるので、読み手にとってストレスのない読み物になります。
見出しを使うと、長い文章がパッと見てわかりやすくなります。「何について書かれているのか」が見出しで伝われば、読み手は知りたい情報にすぐたどり着けます。たとえば、こどもでも読める絵本のように、わかりやすい言葉で、短くまとめるのがコツです。難しい言葉を使わず、見る人の気もちになって書くことが大切です。

ブログやホームページを作るとき、少しでも多くの人に見てもらいたいと思って制作します。そんなときに大切なのが「SEO(エスイーオー)」です。これは検索エンジンで自分のページを上のほうに表示させるための工夫のことです。見出しも、その工夫の中でとても大事な部分になります。
SEOとは、検索エンジンで自分のページが見つかりやすくなるようにする方法です。たとえば「おにぎり 作り方」と検索したとき、自分のレシピページが上に出てくれば、たくさんの人に見てもらえます。これがSEOの力です。むずかしいことをしなくても、「読んでくれる人が知りたいこと」をちゃんと書くだけでも効果があります。まずは記事の中に、知ってほしい言葉(キーワード)を入れるところから始めましょう。
検索エンジンは、見出しの中にある言葉をチェックしています。たとえば「かんたんおにぎりレシピ」という見出しがあれば、「おにぎり」「レシピ」といった言葉が検索に使われやすくなります。見出しはページの内容を表す大事なポイントなので、ここにキーワードが入っていると検索にも強くなります。見出しをつけるときは、「どんな言葉で検索されるか」を考えて入れるのがコツです。

見出しを工夫するだけで、記事の見つけられやすさや読まれやすさがぐっと上がります。ただ書くだけではなく、少しのコツを取り入れることで、検索にも強くなり、読者にもやさしいページになります。ここでは、見出しにキーワードを入れる方法や、文字数の目安、見ただけで内容がわかる言い回しについて紹介します。
キーワードとは、読者が検索するときに使う言葉のことです。たとえば「かんたん 朝ごはん」などがそれにあたります。見出しにキーワードを入れると、検索にひっかかりやすくなりますが、入れすぎると読みにくくなります。
ポイントは次の3つです。
見出しは「パッと見て意味がわかる」ことが大切です。長すぎると読む気がなくなり、短すぎると内容が伝わりません。目安としては、20文字前後が読みやすくおすすめです。たとえば「時間がない朝でもできる朝ごはんレシピ」は24文字で、内容がよく伝わります。文章のような長い見出しは避けて、すっきりした言い回しにしましょう。
読者は見出しをざっと見て、「読むかどうか」を決めています。そのため、あいまいな言葉は避け、具体的な言い方を心がけましょう。
たとえば、
というように、内容がイメージしやすい言葉を使うと効果的です。見出しは「伝えたいことを一言でまとめる」イメージで考えてみましょう。

ブログやホームページを作るとき、見出しには「h1」や「h2」などの番号のようなルールがあります。これはパソコンに「ここが大事」「これはその中の小さい話題」と伝えるための目じるしのようなものです。このルールを正しく使うと、読み手にも検索エンジンにもやさしいページになります。
「h1」は記事の中で一番大事な見出し、つまりタイトルに使います。記事の中で1回だけ使うのが基本です。そのあとに使う「h2」は、記事の中の大きな話題をわける見出しです。さらに細かく分けたいときは「h3」を使います。
順番に注意して、
というふうに重ねて使うのがコツです。順番がバラバラだと、読みづらくなったり、検索にも悪い影響が出ることがあります。
具体的に、このページでは
h1:見出しで検索上位へ!ホームページ初心者にやさしいSEO入門
h2:4. 見出しのつけ方ルール:「h1」「h2」ってなに?
h3:4-1. 見出しの順番と使い方のコツ
というように見出しをつけています。
| 見出しの種類 | 使う場面 | ページ内での使い方のルール | 使用回数の目安 |
|---|---|---|---|
| h1 | ページ全体のタイトル | 最も重要な見出しとして1ページに1回 | 1回だけ |
| h2 | 文章の中の大きな話題の区切り | h1の下に配置し、内容を分類する | 複数OK |
| h3 | h2で分けた話題の中の補足や詳細 | h2の下に配置し、内容をさらに分ける | 必要に応じて使う |
WordPressでは、見出しをつけるのもとても簡単です。記事を書く画面で、見出しにしたい文字を選んで、画面上の「段落」や「見出し」というところから「h2」や「h3」を選ぶだけです。文字を大きくするために「見た目だけ」を変えるのではなく、「見出しとして設定する」ことが大事です。見た目ではなく、正しいタグ(h1・h2など)で設定すれば、検索にもやさしい記事になります。最初はh2とh3の使い分けから始めてみると、スムーズに覚えられます。

見出しがうまく書けたかどうか、自分だけで判断するのはむずかしいこともあります。そんなときは、見出しをチェックしてくれるツールを使うと便利です。点数をつけてくれたり、改善のアドバイスをくれたりするものもあり、初心者でも安心して使えます。
見出しスコアとは、見出しの良さを数値で評価してくれるしくみのことです。たとえば、あるキーワードがちゃんと入っているか、文字数が長すぎないか、読みやすいかなどを見て、点数を出してくれます。有名なツールに「CoSchedule Headline Analyzer(コスケジュール・ヘッドライン・アナライザー)」があります。使い方はかんたんで、見出しを入力するだけ。点数が出るので、どこを直せばいいかがひと目でわかります。
以下の表に、3つの見出しチェックツールの特徴と違いを簡単にまとめました。
| ツール名 | 無料/有料 | 特徴 | 日本語対応 |
|---|---|---|---|
| CoSchedule Headline Analyzer | 無料 | キーワード・文字数・感情などをスコア化 | ×(英語のみ) |
| 無料のAIタイトルジェネレータ | 無料 | キーワードを入れると見出しを自動提案 | ○ |
| ChatGPT | 無料〜有料 | 見出し案を柔軟に生成・修正できる | ○ |
スコアが思ったより低かったときは、見出しの中身を少し見直してみましょう。
改善のポイントは次のようなことです。
見出しの意味がしっかり伝わるように意識して、まずは1つだけでも直してみると、少しずつコツがつかめてきます。

見出しは、記事の内容がひと目で伝わるように、短くてわかりやすい言葉で書きましょう。検索されやすいキーワードを自然に入れるのがコツです。たとえば「朝ごはん かんたん」のような言葉を入れると効果的です。まずは、読者が何を知りたいかを考えて、それを見出しにしましょう。
見出しとは、記事の中で「ここからはこの話ですよ」と知らせるための目じるしのことです。たとえば料理レシピなら「材料」「作り方」などが見出しになります。見出しがあると、読む人が内容を探しやすくなり、ページ全体がすっきりと見やすくなります。
h1タグは、ページの一番大事な見出し、つまり記事のタイトルに使うものです。1ページに1回だけ使うのが基本です。検索エンジンもこの部分を特に重要だと見ているので、記事の内容をよく表した短い言葉で書くと効果があります。
見出しの文字数は、だいたい20〜30文字が読みやすいとされています。長すぎると読みづらくなり、短すぎると内容が伝わりません。読者が内容をすぐに理解できるように、伝えたいことを簡潔にまとめましょう。
h2の見出しは、記事の中の大きな話題を分けるときに使います。20〜30文字くらいを目安に、内容がひと目で伝わるように書くと効果的です。キーワードを1つ入れて、文章の流れに合った言い回しを心がけましょう。
見出しとSEOの基本がわかったら、実際に記事を作って試してみましょう。まずは短いブログや紹介ページからはじめるのがおすすめです。自分のペースで少しずつ進めてみてください。